2023年11月15日付で日本デザイン学会『デザイン学研究特集号』30巻2号(通巻108号)が発行されました。*1。
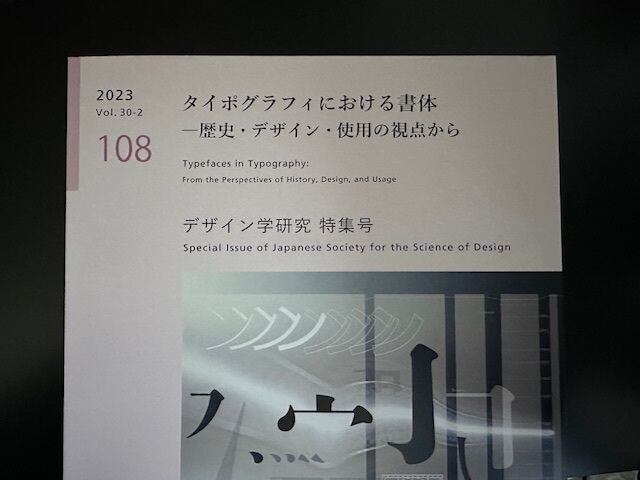
副題が「タイポグラフィにおける書体 ―歴史・デザイン・使用の視点から」とされているタイポグラフィ研究の特集号で、次の内容となっています。
- 巻頭言 伊原久裕「特集テーマ「タイポグラフィにおける書体」について」
- 歴史
- デザイン
- 髙城光「蔡国金文書体の様式と再現」
- 新海宏枝「ひらがな書体「れんぴつ60」のこと:仮説と検証」
- 野宮謙吾「既存書体の合成を手法とした漢字書体作成の実験」
- PUNSONGSERM, Rachapoom「Approach to Design Roman Letterforms Effective in Low Visual Acuity: Prototype of Roman UD Typeface」
- 使用
巻頭言にある通り、『デザイン学研究特集号』30巻2号(通巻108号)は、2010年の特集号「タイポグラフィ研究の現在」(17巻2号 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jssds/17/2/_contents/-char/ja)、2011年の「タイポグラフィの史的研究」(19巻3号 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jssds/19/3/_contents/-char/ja)、そして2016年の「タイポグラフィへの視点」(23巻2号 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jssds/23/2/_contents/-char/ja)に続く、日本デザイン学会タイポグラフィ部会としての通算4回目のタイポグラフィ特集号ということになるそうです。
私は「近代和文活字書体史・活字史から19世紀印刷文字史・グローバル活字史へ」という小文を書かせていただきました。全8ページを次のように細かく刻んでいます。
- 近代和文活字の仮名書体史
- 近代活字の前史イメージ
- 和文活字書体史研究上の大きな課題としての仮名書体史研究
- 近代活字の前史イメージ
- 築地活版製仮名書体の歴史的分析と分類への取り組み
- 築地五号の歴史的分析
- 和文ルビ活字の歴史的分析
- 築地活版製号数活字の仮名書体に関する分類の試み
- 築地五号の歴史的分析
- 「和様」ひらがなと楷書漢字を組み合わせることは不思議あるいは不自然なことだったか
- 近世の漢字平仮名交り文に見られる「和様」仮名の存在
- 楷書の漢字と「和様」ひらがな交じりのケース
- 近世の漢字平仮名交り文に見られる「和様」仮名の存在
- ひらがなを四角の中に押し込めることは近代活字創成期の創意工夫だったか
- マス目揃えと放ち書き
- いろはの手本と枠内に収められる平仮名の姿
- マス目揃えと放ち書き
- 和文号数活字と19世紀前半の英米系活字サイズの実態と関連性
- 日本における「明朝」「活字」という語の使用は近代活字以前に大きく遡る*2
- 日本で活字という言葉はいつごろから使われているか
- 印刷文字の書風を指す「明朝」という語の早期使用状況
- 英語圏で「Movable Type」に類する言葉はいつごろから使われているか
- 日本で活字という言葉はいつごろから使われているか
- むすび:19世紀印刷文字史・グローバル活字史という枠組みの必要性
今回の小文は、2010年の『デザイン学研究特集号』17巻2号の小宮山博史「和文活字書体史研究の現状と問題点」(https://doi.org/10.11247/jssds.17.2_42)と、小宮山博史『明朝体活字 その起源と形成』(2020年、グラフィック社 http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=42704)を強く意識して書いたものです。
日本で近代和文活字の歴史・活字書体の歴史――とりわけ幕末・維新期を起点とする最初の世代のこと――を記録や調査研究の対象とする人々を、三谷幸吉・川田久長時代、佐藤敬之輔・矢作勝美時代、小宮山博史・府川充男時代という具合に整理することができると思います。それぞれの時代に、前代の宿題が解決されたり、新しい課題が見出されたりしながら、近代和文活字の歴史や活字書体の歴史について、従来視界に入っていなかったものが見えてきたり、ぼんやり見えていたものがより高い解像度で理解できるようになってくるイメージです。
ここ20年ほど多種多様な資料を漁って府川充男『聚珍録』(2005年、三省堂、https://web.archive.org/web/20160911091957/https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/syuchinroku.html)の隙間をチマチマと埋めていく作業を重ね、私の中で育ってきた観点が、「近代和文活字書体史・活字史から19世紀印刷文字史・グローバル活字史へ」というものになります。
「近代和文活字史から19世紀印刷文字史へ」となる部分は、佐藤敬之輔から小宮山博史へと引き継がれた課題のひとつである和文活字書体の分類や成立事情について、特に「近代和文活字書体」草創期のことを考えていくには「19世紀印刷文字史」とでもいう枠組みで維新以前との連続・不連続を改めて見直す必要があるのではないかという問題意識を示すものです。
「近代和文活字史からグローバル活字史へ」となる部分は、川田久長から小宮山博史へと引き継がれた課題のひとつである欧米発の号数制明朝体活字の成立と日本での展開について、鈴木広光氏*3や、蘇精氏*4、Michela Bussotti・Isabelle Landry-Deron両氏*5などによる、欧米での漢字活字開発そのものの歴史を掘り下げることの他にも、まだまだ掘り拡げて考えるべき点がありそうだという問題意識の発露です。
非常に大きなテーマを8ページで圧縮展開した結果、伝わるものも伝わらなくなっているのではないかという懸念はあるのですが、図書館等でアクセス可能な方、ぜひとも御高覧いただき、御批判と御批正を賜りますようお願い申し上げます*6*7。
以前『ユリイカ』2020年2月号に書かせていていただいた「近代日本語活字・書体史研究上の話題」(注釈リンク集:https://uakira.hateblo.jp/entry/2020/01/27/000000)は、特に活字・書体史研究の「方法について」書き残しておきたいと思ったものでした。併せてご覧いただければ幸いです。
*1:通例では次の号が発行されたら https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jssds/_pubinfo/-char/ja でオープンアクセス化されるのですが、2023年12月にオープンアクセス化されました。
*2:「日本における「明朝」「活字」という語の使用は近代活字以前に大きく遡る」の項は、上海美術学院から近刊予定の論文集に寄稿した「日本で活字という言葉はいつごろから使われているか、またそれはMovable Typeの訳語なのかどうか」という小文をダイジェストしたものになっています。昨年Facebookで公開した日本語原稿のURIを参考に掲げてあるのですが、印刷されたURI文字列をたどるのがしんどいので、ここにリンクを貼っておきます:https://www.facebook.com/uakira2/posts/pfbid0KNPk7yAvrGciWKauur8dZZFFhP6ZbQamBqCzgJJ2z4vCRAi4pThKZNLV8VnfQphwl。冒頭に2023年刊行予定と記しましたが、2024年以降の模様です。併せてご高覧いただければ幸いです。
*3:①鈴木広光「ヨーロッパ人による漢字活字の開発―その歴史と背景」(印刷史研究会編『本と活字の歴史事典』所収、2000年、柏書房)、②『日本語活字印刷史』(2015年、名古屋大学出版会 https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0795-5.html)等
*4:①蘇精(Su, Ching)「The printing presses of the London Missionary Society among the Chinese 」(1996年、UCL https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1317522/)、②「美華書館二号(ベルリン)活字の起源と発展」(『書物学』15巻所収、2019年、勉誠出版 https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=101002、③「ウィリアムズと日本語活字」(『活字 近代日本を支えた小さな巨人たち』展覧会図録所収、2022年、横浜市歴史博物館、https://yokohamahistory.shop-pro.jp/?pid=171817733)等
*5:Bussotti = Landry-Deron「国立印刷局の漢字木活字(Printing Chinese Characters, Engraving Chinese Types: Wooden Chinese Movable Type at the Imprimerie Nationale (1715-1819)」https://uakira.hateblo.jp/entry/2020/07/12/172904
*6:繰り返しになりますが、掲載誌『デザイン学研究特集号』30巻2号は、次の号が発行されたら https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jssds/_pubinfo/-char/ja でオープンアクセス化されます
*7:12月17日追記:2023年12月にオープンアクセス化されました。