以前「新聞活字サイズの変遷史戦前編暫定版」のコメント欄に短く記していた「都式活字(都式新活字)の大きさを9ポイント7分5厘(9.75pt)ではなく9ポ半(9.5pt)相当と判断する理由」を、少し丁寧に補足しておきます。
都式活字のデビュー
1月28日以降、都新聞の紙面は本文五号活字1行22字詰・1頁6段組から、都式活字1行21字詰・1頁7段組に変わっています。
『印刷雑誌』12巻1号(1902年1月)の雑纂欄「都新聞社ノ新活字鑄造」には次のように評されていました(https://dl.ndl.go.jp/pid/1499043/1/17)。
都新聞社ニ於テハ此度新ニ五號ト六號トノ相形大ノ活字ヲ創鑄シテ現ニ本月末ヨリ之レヲ使用シ印刷發行シツヽアリトイフ果シテ將來ニ於テ弘ク世間ニ使用サルヽヤ否ヤハ豫想シ得ザレトモ*1兎ニ角活版界ニ於テハ注目スベキ新事業トイフベク吾人ハ同社ガ獨リ他ニ卒先シテ此擧ヲ斷行シタル勞ヲ多トスルモノナリ
この頃の新聞では記事の構成に本文の基本活字である五号活字とルビ活字(七号活字)、商況欄などの六号活字、中見出しなどの四号(三号)活字、大見出しなどの二号活字という、都合5~6種の大きさが併用されていました。
明治35年の段階で『都新聞』本文活字とルビ活字が都式活字になりましたが、他は従来の号数活字が併用されている状態が続きます。その後まずは明治36年9月22日付社告での予告通り、同年10月1日から「都式二号活字」が使われるようになりました。「都式二号活字」は、「都式活字」の縦横2倍の活字です。
以降、活字サイズについて紙上での直接的な言及は無くなったようですが、復刻版で紙面の変遷を追ったところ、
都式活字の大きさ――従来説「9.75pt」の成り立ち
高野久太郎編『活版印刷術』(高野久太郎、大正4年)では欧文活字と和文活字の対応表で「10ポイント ロンプライマー (所謂都式活字)」とされています(https://dl.ndl.go.jp/pid/1183187/1/27)。これは都式活字の大きさがが10.0アメリカンポイントだという意味ではなく、9ポイント活字と五号活字(Small Pica相当)の間の大きさだ、という程度の話です。
大正4年に開催された印刷青年会講演大会の講演「日本のポイントシステム」で東京築地活版製造所の野村宗十郎は「此の都式なるものは何らの標準があつた譯でない」と評していたようです(『日本印刷界』68号〈大正4年6月〉https://dl.ndl.go.jp/pid/1517487/1/50)。先日来言及している大正7年『日本印刷界』105号の野村宗十郎「日本に於けるポイントシステム」では「然しこれは尺度にも何にも據るべき所がなかつたのである」という表現になっています(https://dl.ndl.go.jp/pid/1517524/1/29)。
『印刷雑誌』
明治30年代前半までの各紙が「五號二十二字七段といういかにも締りのない、且つ段數の都合の惡いもの」(強調:引用者)であったところ、当時の都新聞総監督である岡本甚吉が「活字縮少によつて字數を增加するの必要なるを認め」「二十一字詰八段制となし而かも外観の同一なるべき相當の字格を得るに苦心し」(強調:引用者)ていたが、「現在の善勝堂の管理者木戸善輔氏が都新聞工場に入つて來た」ことから「木戸氏が善勝氏の門人であり姻戚であつた關係上、直ちに善勝氏に謀」り、後の都式活字が案出された。
岡本氏の語る所に依るも當時の苦心は一通りのものでない。今のポイント計があつて大小の區別が明確に規定せられる樣な事がなかつたので、新聞輪轉機の胴の大きさから割り出したものであるといふ。斯くして極めた文字は丁度九ポイント七分五厘に相当して居たことがのちに分つたのであつた。
復刻版を見る限り、都式活字を採用する直前の『都新聞』は本文五号活字22字詰6段組という体裁でした。これが都式活字の採用によって21字詰7段組という体裁に切り替わります。祖父江慎さんがお持ちの原紙でも、そのような体裁になっていることが確認できます(2021年7月31日付
この後も津田伊三郎編『本邦活版開拓者の苦心』(津田三省堂、
おそらく「都式活字で有名な松藤善勝の偉業」の記述に輪転機メーカー名を追加したものと思われる表現を、牧治三郎が『京橋の印刷史』に記しています(23頁:https://dl.ndl.go.jp/pid/12047860/1/50)。
松藤が有名になったのは、明治三十三年十月、都新聞のためにマリノーニ輪転印刷機胴から割出した九ポ七五の都式活字創製である。一時は、東京築地活版製造の九ポ及十ポと対抗、万朝報の扁平活字と三ツ巴になって、新聞界を風靡した。
牧以降は概ね、都式活字については「マリノーニ輪転印刷機胴から割出し」た「9.75pt」と語るのが常道になっています。
なお、『日本印刷大観』(東京印刷同業組合、
都式活字の大きさ――現存印刷物の計測から「9.5pt相当」と判断
手元にある都式活字21字詰7段組時代の『都新聞』原紙(明治38年5月1日付)に活字スケールをあててみると、21字詰1行分での結果ですが、9.5ptになっています。
この『都新聞』原紙(明治38年5月1日付)は強い折り癖がついているのですが、天地罫間隔を計ると内々で502~503mmほどでした。紙面の構成は1行21字・1頁7段(長手方向147字)ですから、段間6箇所と天地の罫と本文の間計2箇所の合計8箇所が全て0.5字分程度の幅と見ておくと、{147字+(8箇所×0.5字分=4.0字)}× 都式活字サイズ=502mm(≒1428.6pt)~503mm(≒1431.4pt)というわけで。これを逆算すると都式活字サイズは9.46~9.48pt程度となります。
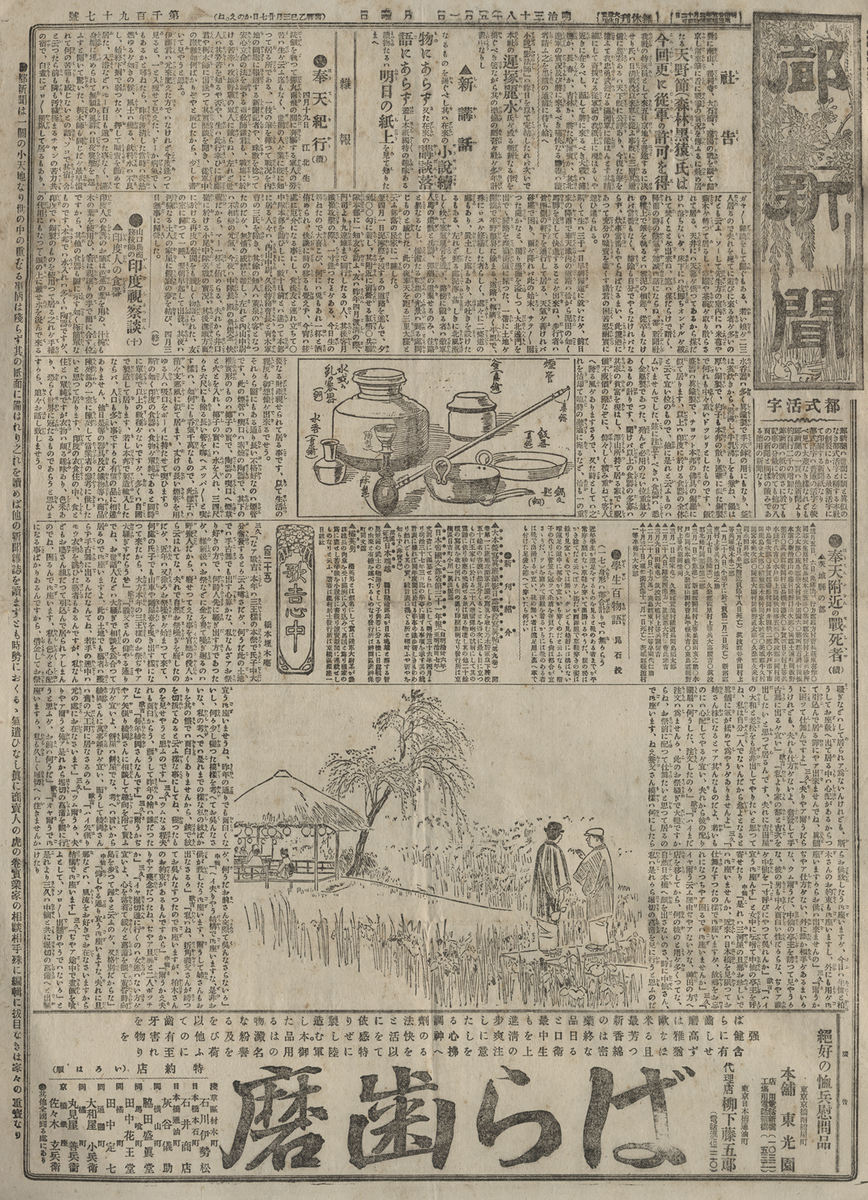
想定段間の見込み違いや、折り癖の影響を除ききれておらず天地罫間隔を正確に測りそびれているといった可能性がある他、これらが正確であったとしても現存印刷物の寸法が原版の寸法よりも若干縮んでいる可能性がある――一般に紙型鉛版は原版よりも縮むと言われている――ことから、「9.46~9.48pt」という算出値は「9.5pt相当」と見て良い誤差の範囲と考えています。
実は10年ほど前に、当時「近代書誌・画像データベース」として運用されていたサイトで、巌谷小波『小波身上噺』(大正2、志鵬堂書房)の印刷者が松藤善勝堂であることを知り*3、地元図書館経由の相互貸借で鹿児島県立図書館蔵本を閲覧して本文活字を計ってみたところ、やはり9.75ptではなく9.5ptと判断するのが妥当な数値でした。今般「日本の古本屋」経由で『小波身上噺』を入手したので改めて活字スケールで本文活字38字詰1行分を計測した結果は、やはり9.5pt相当です。

明治35年に刷られた『都新聞』『都の華』の印刷文字が原版の寸法よりも縮んでいる可能性について
さて、先ほど言及した「現存印刷物の寸法が原版の寸法よりも若干縮んでいる可能性」について検証しておきましょう。
『都新聞』の本文活字が旧五号から都式活字に切り替わるころに発行されていた附録『都の華』は、第1号から、ちょうど本紙で都式活字を採用することとなった
令和3年度まで「小石川図書館」と名乗っていて4年度から「中央図書館」へと名称を改めた山形大学附属図書館中央図書館が、CiNiiブックスでは検索ヒットしないけれどもこの時期の『都の華』を所蔵していると9年前に気づいていたものの(https://x.com/uakira2/status/778240350603194368)、なかなか訪問のチャンスに恵まれていなかったのですが、最近になって(?)学外者でも(学生休業期以外は)土日祝でも利用可能になっていたことに気づき(「学外の方へ(利用案内)」https://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yktop/k-guide/k-gakugai/)、51号までの『都の華』原紙と、52号以降の原紙を計ってきました。
通常の定規と、祖父江慎さん設計のモリサワ「伝統的文字サイズ表」による計測で、以下のリンクは国書データベース(旧・近代書誌・近代画像データベース)の当該号とします。
- 51号:版天地220mm、本文五号活字(築地体前期五号)(https://kokusho.nijl.ac.jp/kindai/OWNDT-00326)
- 52号:版天地213.5mm、本文9.5pt活字(都式活字)(https://kokusho.nijl.ac.jp/kindai/OWNDT-00325)
仮に52号以降の本文活字サイズが9.75pt相当であったなら、2.6%縮んでいることになりますから、五号活字時代の本文活字は10.78pt程度のものが2.6%ほど縮んで見えていることになります。MacKellar社の旧式Small Pica(略82行/呎:約10.6pt)やCaslon社の旧式Small Pica(略83行/呎:約10.4pt)の範囲をこれほど逸脱する旧五号活字という存在は確認されていませんから、このような縮小はかかっていないと考えて良いでしょう。
『都の華』原紙測定の結果からは、「現存印刷物の寸法が原版の寸法よりも若干縮んでいる可能性」については、仮に伸縮があったとしても捨象して良いレベル(多く見ても1%未満)と思われます。
旧五号時代の『都新聞』(明治35年1月25日付5135号)原紙と、都式活字に切り替わった日の『都新聞』(明治35年1月28日付5137号)原紙をお持ちの祖父江慎さんが以前SNSで本文活字サイズについて言及されていた際にも、旧五号期はモリサワ「伝統的文字サイズ表」で五号活字に該当、「都式新活字」は9.5ポイント活字に該当する様を添付画像でお示しくださっていました(2021年7月31日付
やはり、伸縮の可能性は捨象してよく、かつ「都式活字(都式新活字)」の大きさは9ポ半(9.5pt)相当と考えるのが妥当でしょう。