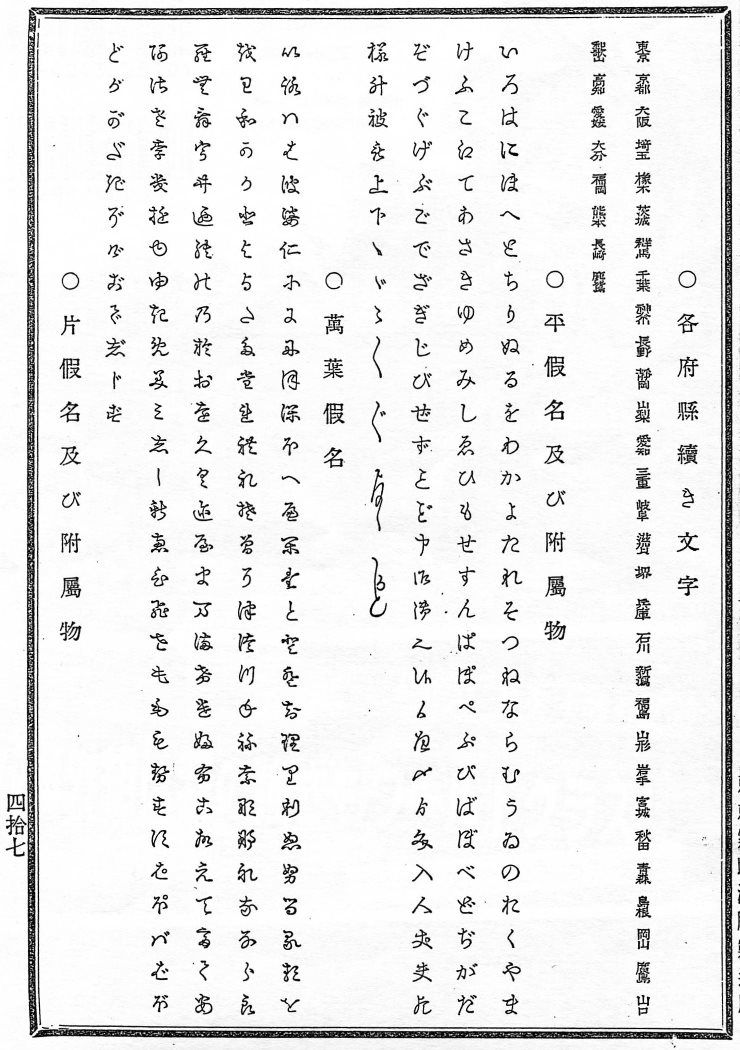過日ツイートした通り、研究者番号を持っていなくとも論文(あるいはそれに類する著作物等)があれば登録できる研究者ポータル・研究者データベースであるresearchmap(の中の人)が、我々「在野研究者」「日曜研究者」「野良研究者」「独立研究者」「フリー」等を統合する「所属」属性ラベルに関する意見を募集中だ。
次期researchmapの所属分類について、現在「フリーランス」という分類があります。これを「フリーランス・独立系」としたほうがよいというご意見があります。賛否をお知らせください。 #researchmap
— norico arai (@noricoco) 2017年4月19日
事の経緯はtwitter/@naka3_3dsukiさんによるTogetterまとめ「リサーチマップ(researchmap)の登録者の新しい区分について」や、同氏のブログ記事「【ニュース】researchmap登録者の新しい区分に図書館司書・学芸員ほか色々と検討開始」に記されている。
ところで、《我々「在野研究者」「日曜研究者」「野良研究者」「独立研究者」》のうち、英語でいう「Independent Scholar(またはIndependent Researcher)」の訳語として相応しいものは、どういうものだろうか。
2017年4月21日現在、「Independent Scholar」で検索すると第1位がWikipedia英語版の当該項目である。
第2位が「independent scholar の訳語 - TOEFL・TOEIC・英語検定 解決済 | 教えてGoo」になっており、「独立研究者、在野の研究者、など言い方はいくつかあるかと思うのですが、新聞などで表記する際independent scholar をどう訳しているのか知っていたら教えてもらえると嬉しいです。」という質問に対するベストアンサーとして、次の回答が掲げられている。
在野研究者
在野学者
独立系研究者
など使用例:
http://www.asahi.com/international/weekly-asia/TKY201109190083.html
http://mainichi.jp/s/it/news/20110608k0000m030084000c.html
回答中で示されているURLはどちらもリンク切れになっているが、前者(2011年9月19日付朝日新聞「週刊アジア」コーナーの記事)はインターネットアーカイブに蓄積されており、「交易の島、共通語生む インドネシア ことばを訪ねて(1)」と題する、「在野研究者」用例の記事であることが判る。後者はインターネットアーカイブにも残されていないが、2011年6月8日付毎日新聞の「Independent Scholar」関連記事であることから、G-Searchにより、同日付の東京朝刊国際面に掲載された「米グーグル:Gメール攻撃「単純だが大胆な手口」専門家。2月に警告」と題する「独立系研究者」用例記事であることが判る。
このように例示されると、「在野研究者」はどちらかというと「Scholar out of power」などだろうから「Independent Scholar(Researcher)」は「独立系研究者」だな――と思ってしまいがちだが、この「回答」は2017年の我々にはふさわしくない。
「我々」の自称で(も)あり得る「フリー研究者」「在野学者」「在野研究者」「自主研究者」「自由研究者」「自立研究者」「独立系研究者」「独立研究者」「日曜研究者」「無所属研究者」「野良研究者」のキーワードでG-Searchしてみたところ、次のような結果を得た*1。
グラフに掲出していない「自主研究者」「無所属研究者」「野良研究者」は0件。「自由研究者」は1997年6月18日付日本工業新聞の「動燃改革検討委員会 座長試案」1件のみ。「自立研究者」も、2014年6月23日付日刊工業新聞の「13年度版の科学技術白書、高度研究人材の流動性・多様性の向上を重視」1件のみ。
「独立系研究者」は1990年〜2016年の期間に3件しか使われておらず、5件使われた「日曜研究者」や10件使われた「在野学者」、17件使われた「フリー研究者」よりも少ない(上記〈Gメール攻撃〉の記事は、希少用例を一種の典型例として示してしまった、不幸な回答である)。
2016年に荒木優太『これからのエリック・ホッファーのために/在野研究者の生と心得』(asin:9784487809752)が刊行されるなど本命と目される「在野研究者」はこの期間に73件、対抗となる「独立研究者」は110件使われている。
「独立研究者」は、グラフに表れている通り、2000年代に入って急速に世間に浸透してきた言葉といえる。一方の「在野研究者」はこの期間コンスタントに使用されているだけでなく、例えば「本務校をもたない非常勤講師の問題・在野研究者の問題(婦人研究者問題全国シンポジウム)」(1975年11月『日本の科学者』)のような今日的問題を含む40年前の用例があったりするように、古くから「我々」のことを指し示す言葉として使われ続けている(《これからのエリック・ホッファーのために》が「在野研究者」の語を選んでいるのも、同書が歴史に学ぼうとする本だからであろう)*2。
ともあれ、「フリーランス・独立系」という形で「独立系」という文字列を目にすると、「政府系シンクタンク」「独立系シンクタンク」などと言う時の「独立系××」に所属しているかのように感じてしまうし、「独立系研究者」の省略形だとするなら、実は前述のように「独立系研究者」の語は「Independent Scholar/Researcher」の訳語として今採用するべきではない。仮に〈フリーランスや独立研究者などに類する系統の方々〉の意味であるとしても「フリーランス・独立」「フリー・独立」「フリーランス・独立研究者」などに改めていただいた方がいいように思われる。
ここまでお読みいただいたあなたは、例えば中学校や高校で教鞭を執る傍らで研究活動を行う、しかも科研費を取得した研究活動まで行い成果を挙げている、そのような研究活動の中で「あなたは研究者では無い」という理由で資料へのアクセスを拒まれた経験をお持ちであったりしないだろうか。
また別のあなたは、建前上申請できるはずの科研費について、研究者ではなく教員として雇用される非常勤だからと、「所属先」から手続きを拒まれるような経験をお持ちであったりしないだろうか。
更に別のあなたは、「所属先」から定年退職して以降も自分自身の研究活動を継続している、そのような研究者であったりしないだろうか。
あなたがたもまた、我々Independent Scholarの仲間に他ならない。
Wikipedia英語版のIndependent Scholarの項を見ると、アメリカ「National Coalition of Independent Scholars」、カナダ「Canadian Academy of Independent Scholars」、オーストラリア「Independent Scholars Association of Australia」等、諸外国では我々「独立研究者」をサポートする組織が活動しているのだという*3。
「有所属研究者」が研究活動を寡占している「異常な」時代は、おそらく少子高齢化と情報化によって緩やかに終わりつつあり、我々Independent Scholarもまた(歴史的には常に既に)「裾野」とは限らない学術の担い手であることが社会的に認知されつつある、そのような時代に世界が変わりつつあるのだろう。
《これからのエリック・ホッファーのために》が示すような形で、個々人の努力と根性と幸運に頼って研究を進めざるを得ない「在野研究者」の時代を、2016年で終わらせてもよいのではないか。
researchmapに登録することで「独立研究者」という研究者であることがオーソライズされる、そしてそのような「独立研究者」の研究活動がNCISのような組織によってサポートされる、――そのように「社会の仕組み」によって「独立研究者」の研究活動が行われるような未来が、この日本でも今まさに切り開かれて、良いのではないか。
吾輩は「独立研究者連盟」所属である。連盟はまだ無い。