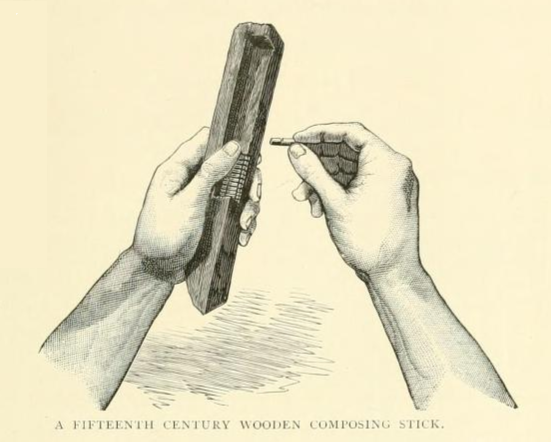1850年頃に上海のロンドン伝道会印刷所で使われていたLong Primer活字の大きさが、1841年頃のロンドンの主要活字会社の活字サイズに当てはまらないように思われる寸法だったため、この「小さな Long Primer活字」の来歴について何を手がかりに探せばいいのか困惑していた。
LMSアーカイブから購買の記録が見つかるようなことがあればベストなのだけれども、そういった記録が残っていなかった場合に役立つような傍証的な手がかりが得られないものかという悩み。
やはりJames Mosley『British type specimens before 1831: A hand-list』(1984, Oxford)の終盤や、それに続く年代の資料を地道に探さなければならないのだろうか……と思っていたところ、『Studies in Bibliography』に掲載された論文一覧にJohn Richardson Jr.「Correlated Type Sizes and Names for the Fifteenth through Twentieth Century」というペーパーがある(「SB」43巻251-272頁)ということに気がついた。
これは正に探し求めていたテキストなんじゃないかと大きな期待を持って読んでみたら、想像していたものとはだいぶ違った内容だった。
改めて自ら一次資料を計測してその結果を一覧形式に集計したというような性質のものではなく、過去様々に積み上げられた先達の資料を一覧表形式に落とし込みましたよというものだったのだ。かなり〈広く浅く〉なので、いま己が問題にしている〈19世紀後半の英米における様々な活字ベンダーの違い〉であったり、同じ時期のフランスやプロイセンの状況がどうであったかというようなことを知るには役立たない。
Richardson Jr.の執筆の動機として、研究者用の便利ツールを意図して書かれたJohn Tarr「The Measurement of Type」(1946/47『Library』s5-1)が存在するが残念ながら「寸法の換算ミスがあったり重大な誤植があったりする」――にも関わらず以後誰も修訂していないこと、またBowersによる「20行サイズ」だけでなくポイント換算値やPica換算値などと併記してあることが便利であること、などと説明されている(Tarrの誤りについては、Gaskell「Type Sizes in the Eighteenth Century」にも言及があった)。
末尾に、〈将来的には基礎資料となるべき活字見本を見定めて直接的に活字サイズが計測されるべき〉であり〈Updikeの「Chronological List of Specimens」*1が参照されよう〉などと書かれているのだけれど、Richardson Jr.自身あるいは他の人物の手によって、そうした後継研究が為されたのかどうか、今のところは判らない。
さしあたり、Richardson Jr.が依拠した先行者のうち、18世紀と19世紀の活字サイズに関するものを拾い読みしておくべきか、と思うので一応メモ。
18世紀の活字サイズについて:
- Harry Carter『Fournier on Typefounding; the Text of the Manuel Typographique(1764-1766)』(1930)のxxxv頁「Table of Body-Sizes」
- Philip Gaskell「Type Sizes in the Eighteenth Century」(1592/53『Studies in Bibliography』5巻。先日記したメモに、Gaskellがまとめた活字サイズ一覧の件で後日何か書き足すかもしれない。)
- Talbot B. reed『A History of the Old English Letter Foundries』(1887←この活字旧称の英仏独蘭伊西語対照表はInternet Archive経由で時折目にしていた。Richardson Jr.の注記によると、A. F. Johnsonによる増訂版が1974年に刊行されているらしいく、「増補」に色々と役立つ内容が書かれているような匂いがする。)
- Allan Stevenson『Catalogue of the Botanical Books in the Collection of Rachel McMasters Miller Hunt』第2巻第1部「Introduction to Printed Books, 1701-1800」(HathitrustでFull Viewになっているのは2巻2部であるのが残念。国内では科博と京大理学部が持っていて、リプリント版を国際日本文化研究センターが所蔵。)
19世紀の活字サイズについて:
- Giambattista Bodoni『Manuale Tipografico』(1818)(Richardson Jr.は、この第1巻1-144頁に掲げられているローマン体について直接計測して「20行サイズ」を得、Appendix Aに取りまとめている。)
- Charles H. Timperley『The Printer's Manual』(1838、リプリント版1965)(56頁の、英仏独蘭対照表および〈EM/ft単位による〉英系標準活字サイズ表に言及あり。)
さて、Richardson Jr.によるGiambattista Bodoni『Manuale Tipografico』(1818)の活字サイズ測定について。
「直接計測」は好ましく、また大型活字の場合「20行」も纏めて組まれることがないため「何行分を計測して得た値なのか」が記されているところはとても良い。見習いたい。

一方、ポルトガル国立図書館のデジタル化資料――残念ながら71頁「Soprasilvio/1」など欠けているシートがある――を見る限り、最小のParmigianina活字から19番目の大きさになるDucale活字あたりまでは行間ベタのsolidな組見本ではなくインテルが入ったLeading組なのではないかと思えてならない。Solid組である可能性が高そうなのは20番目の大きさになるReale活字から最大のPapale活字までの3種類だけなのではなかろうか。Leading組ではなく大きな余白を取って鋳造された活字のsolid組なのだという傍証がどこかで得られるのだろうか。



というわけで、振り出しに戻る。Mosley『British type specimens before 1831: A hand-list』をポチってしまった。
船便で届くまでの間に、「20行サイズ」の扱いに関する基礎テキストであるというFredson Bowers『Principles of Bibliographical Description』(初版1949、再版1962、1986)やG. Thomas Tanselle「The Identification of Type Faces in Bibliographical Description」(1966『Papers of the Bibliographical Society of America』60巻2号) を眺めておけるだろうか*2。
*1:『Printing Types, Their History, Forms, and Use』の巻末リスト:https://books.google.co.jp/books/about/Printing_Types_Their_History_Forms_and_U.html?id=5-GAMqFaD3gC&redir_esc=y
*2:JstorでG. Thomas Tanselle「The Identification of Type Faces in Bibliographical Description」を閲覧できるようになるのは1か月ほど先の話。